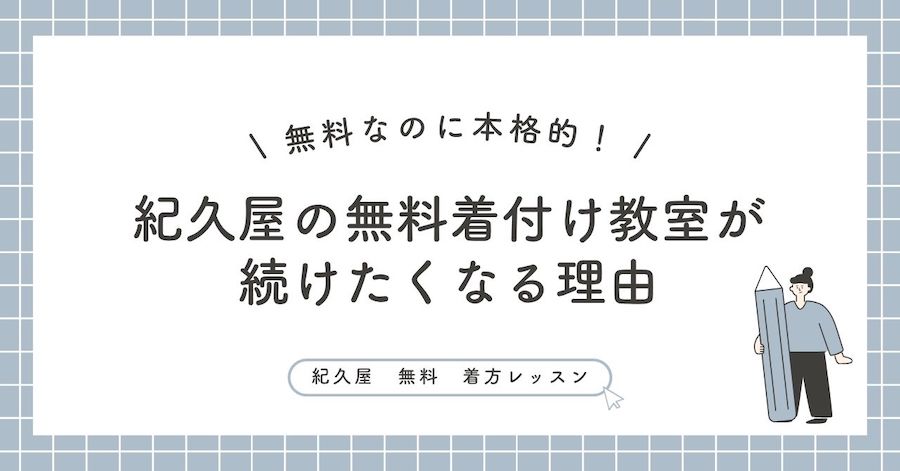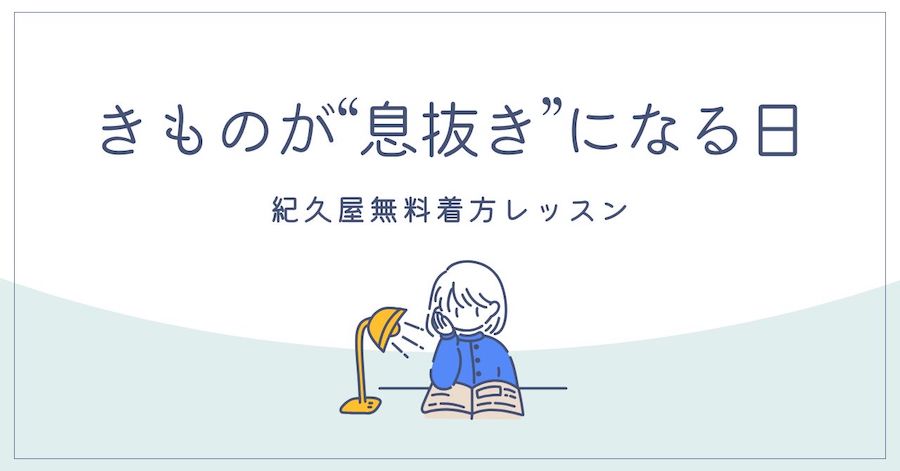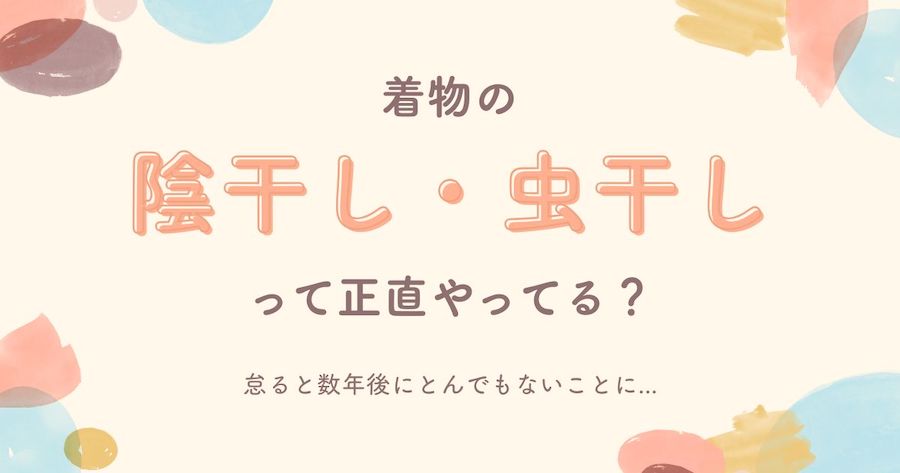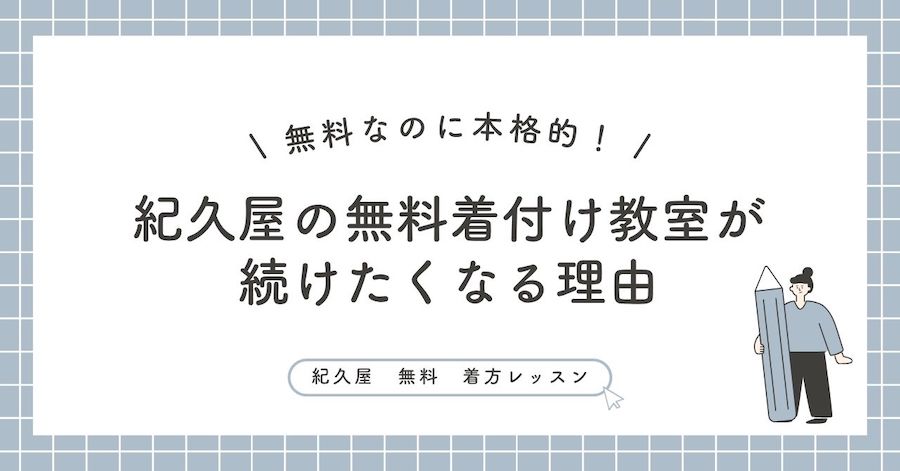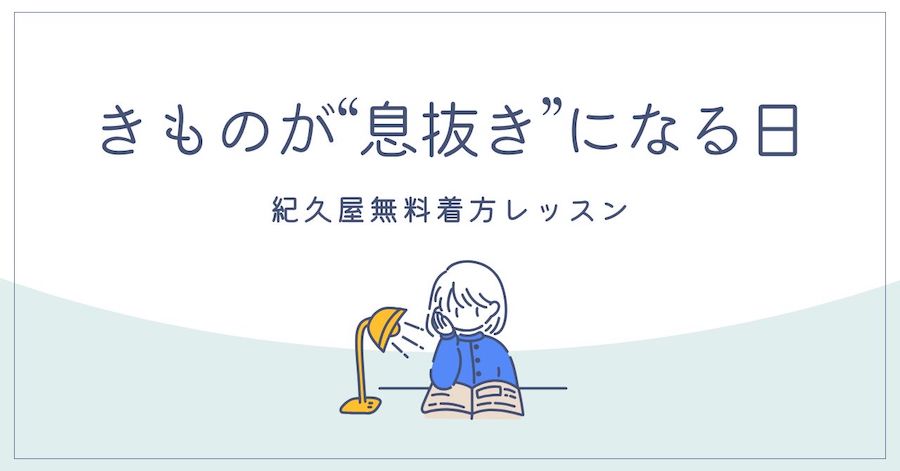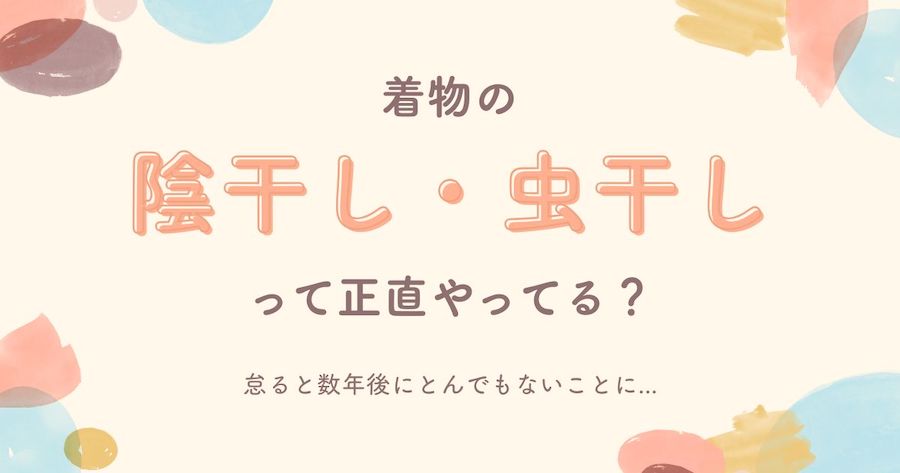 「陰干し」「虫干し」
「陰干し」「虫干し」
言葉は聞いたことがあるけれど、きちんとやってますか?と聞かれると、
少しドキッとしてしまう方も多いのではないでしょうか。
押し入れの中に眠ったままの着物。
「たまに出して風を通してあげたほうがいいのは分かってるんだけど…」
「あの時着た後に何もせずしまっちゃったかも...」
そんな声を、実際にお客様からもよくお聞きします。
でも実は、着物をしまいっぱなしにすることはとても危険なのです。
着用してから数年後、いざ着よう!と思って
タンスから出してみると、
「うっすら黄ばみが出ていた」「なんだかカビのにおいがする」
そんな“悲しい再会”になってしまうことも.....
絹でできている正絹の着物は、
まさに生きている素材と言っても過言ではありません。
湿気を吸ったり吐いたり、季節が変わるごとに呼吸をしながら
一年を過ごしているのです。
だからこそ、たまに空気にふれさせてあげることがとても重要です。
陰干しと虫干しは、絹が呼吸するための大切な時間。
面倒に感じてしまいがちな人が多い作業ですが、
実はこれこそが大切な着物を美しいまま長く楽しむための
一番の秘訣です。

陰干しと虫干しって何が違うの?
陰干しと虫干しってよーく似ている言葉ですが、
実は目的もするタイミングも違うんです。
この2つを正しく覚えておくことで、
大切な着物をより長く美しいまま保つことができます。
陰干しとは?
陰干しは、
着物を着た後に湿気を取り除くためのお手入れ方法です。
汗をかいていないと思う日でも、意外と帯や脇の部分は
汗をかいてしっかりと湿気を含んでいます。
着用後に必ず行うのが
陰干しです。
虫干しとは?
一方、虫干しは
防虫・防カビが目的のお手入れ方法です。
昔から日本では年に3回ほど季節の変わり目に
タンスの中身を虫干しするという習慣がありました。
衣替えの季節に行うだけで、虫食いやカビのリスクをグッと下げられます。
つまり...
陰干し=着た後に湿気を撮るために行う虫干し=虫やカビの発生予防のために衣替えの季節に行うというイメージです。
どちらも風を通してあげることが、
着物を美しく保つ一番のポイントなのです。

今日からできる!陰干し&虫干しの方法
「陰干しと虫干しって、具体的にどうやるの?」
実は、特別な技術も時間もいりません。
ちょっとしたポイントさえ押さえれば、今日からすぐに始められます!
■ 陰干しの手順
1.
天気の良い日を選びましょう。
雨の日や雨上がりなどは湿気がかなり残っているので避けます。
着用後雨の場合は晴れた日に持ち越します。
2.
直射日光の当たらない、風がよく通る場所を選びます。
風が通らない場合は扇風機を離れた場所から弱風で付け、
空気が循環するような環境を作ります。
3. 着物ハンガーに着物・長襦袢・帯をかけ、
風を通すように半日ほど干しておきます。
※汗をかいているようなら、帯揚げも一緒に陰干しします。
4. その後、きちんと折り目通りに本たたみをし、
新しいたとう紙に包んでタンスに収納します。
これだけで着物が含んでいた湿気が抜けて、
手触りがさらりと変わります。
たった数時間のひと手間が、数年後のトラブルを防ぐのです。
空気がカラッとしている夏と秋に行うのがベストタイミングです。
梅雨明けなど湿気がなく、空気が乾いている時期が理想です。
■ 虫干しの手順
1.
晴れていて湿度の低い日を選び、タンスから着物を出します。
2.
直射日光の当たらない風通しの良い場所で半日ほどじっくり風を通す。
3. 干している間に、カビ・よごれ・虫食いのチェック
4. 再びたたんで収納するときは、防虫剤・防湿剤を
新しいものに取り替えます。
◎虫干し時のチェックポイント3つ・衿元にファンデーションよごれがついていないか
・胴裏や八掛にカビの白い点ができていないか
・帯や小物の色移り、シミがないか
もしよごれが見つかったらそのまましまわず、
早めに着物専門店に相談しましょう!
着物のトラブルには早期対応が命なのです。
紀久屋は呉服専門店として、専門の職人による
丸洗いやシミ抜き、洗い張りなど
着物の状態や素材に応じたお手入れを承っております。
「ちょっと気になる...」の段階でお持ちいただくのがベスト!
ご連絡の上、お早めにご持参くださいね。
大切な着物のお手入れは紀久屋におまかせください。

何もしないとどうなる⁉︎ 数年後のリアルな現実
「タンスにしまっておけば安心だよね」と思って、
お気に入りの着物をタンスにしまいっぱなしになっていませんか?
実はその安心、時間が経つほど危険なんです!
着物はとても繊細な糸からできています。
見えないところで湿度を吸い込み、
そして気づかないうちに少しずつ劣化が進んでいってしまいます。
湿気が引き寄せる「カビ・黄ばみ」
着物の保管には桐のタンスが最適とは言いますが、
梅雨の時期などはどうしても湿気がこもりやすい環境です。
締め切ったままだと空気が滞り、
着物が湿気を吸い込んでしまいます。
そして、絹は湿気を吸い込みやすい性質を持っています。
湿気を多く含んだまま置いておくと、
うっすらと黄ばみが出てしまうことも、
カビは湿気と栄養(=よごれ)をよく好みます。
普段の洋服ではなかなか見かけないカビですが、
着物ではわずか数週間で発生してしまうことも。
「着た後の見た目は綺麗だったのに
広げて見たら白い点がちらほら...」
そんな経験をされた方が
紀久屋に相談に来られることも多いです。
基本的にはカビ取りは可能ですが、
広範囲にカビが発生してしまうと痕が残り、
染め直しなど別の加工が必要になることもあります。

気づかぬうちに虫食い被害も
もうひとつ油断できないのが虫食いの被害。
絹やウールの素材は、虫たちにとってまさにご馳走なのです....
とくに汗や皮脂、付着してしまったメイクなどが
少しでも残っていると虫を呼び寄せてしまいます。
「防虫剤があるから大丈夫!」
と思っていても、いつの間にか薬剤の効果が切れていたり、
クリーニングに出さずにしまっておくと
虫やカビを呼んでしまうケースもあります。
何より怖いのは、気づいた時には遅かったということ。
黄ばみやカビ、虫食いは月日を重ねて少しずつ進行する
静かなトラブルです。
着てすぐ後には発生しないのです。
数年経ってから「これってカビ?」「色がちょっとくすんでる?」
と気づくことがほとんどです。
「私が成人式で着た振袖を娘にも...」
「母の形見の訪問着をまた着ようと思って...」
思い出の詰まった着物たちが知らない間に傷んでいたら、
後悔してもしきれませんよね。
そうならないための一番シンプルな予防策が、
陰干しと虫干しなんです。
ほんの半日ほど風を通してあげるだけで、
着物の寿命は何倍にも伸びます。
この一手間が、未来のトラブルを防いでくれるのです。

着物にとっての一番の虫干しは、着てあげること
陰干しも虫干しも、もちろんどちらも大切なお手入れです。
でも実は、着物にとって一番嬉しいお手入れは、
「着てあげること」なのです。
着物を着て歩くことでふわりと風に揺れ、
自然と空気が通ります。
体温で軽く温められ、動くたびに湿気が抜けていく。
実はこれこそが最高の虫干し効果なのです。
「しまいっぱなし」ではなく「着てあげる」
このひと手間こそが、着物の状態を美しく保ち、
自然な風合いを次の世代へとキープしてくれる秘訣です。

どんなに上質な絹でも、ずっとタンスにしまいっぱなしでは
少しずつ呼吸を忘れていってしまいます。
数年ぶりに袖を通すとどこか硬く感じたり、
前とちょっと違うような...そんな経験ありませんか?
それは、着物がずっと眠っていた証拠。
定期的に外の空気にふれさせるだけで、
仕立て上がりのような軽さが保てるのです。
式典などの特別な日じゃなくても大丈夫。
ちょっとしたお出かけやお稽古の日、
お友達とのランチ会...
着物を定期的に着ることで帯の締め方や
裾さばきに慣れ、自分の体に合う着方を覚えていきます。
こうして"自分の着物"として育っていく過程も、
着物の魅力のひとつですね。

大切なのはひと手間と着てあげること
陰干しも虫干しも、特別なことではありません。
風を通してあげるという少しのひと手間です。
ですがこのひと手間が、数年後に大きく影響するのです。
着物の袖を広げた時の空気の香り、
光を受けて浮かび上がる織りの技術、
指に伝わるしっかりとした上質な絹の感触。
着物に向き合う時間を持つことが、
何気ない日常の中で心を整える
特別なひとときなのかもしれませんね。

着物をもっと身近に楽しむために
「久しぶりに着てみたいけど、着方を忘れてしまって...」
「曖昧な部分があって、ネットで調べてもよくわからない...」
という方も多いと思います。
でも大丈夫!紀久屋では何度でも
無料で参加できる
着付け教室を開催しています。
紀久屋では、ベテランの講師が一人一人の
ペースに合わせてしっかり丁寧にサポートいたします。
「難しそう」「不器用だから、、」という方も、
一回目から安心して通っていただけます!
少人数制なので質問しやすく、
わからないところはその場で即解決◎
しかも何度通っても無料なので長く通ってくださっている
生徒さんも多くいらっしゃいます。
練習の後は教室で出会った他の生徒さんとのおしゃべりや、
「この着物素敵ね」「小物の組み合わせがいいですね」
など着物の話題で盛り上がることも。
着物を通じてつながりが生まれていく___
それが紀久屋の着付け教室です。
陰干しや虫干しは、着物を愛おしむための小さな習慣。
そして何より、着ることが1番のケアなのです。
次の晴れた日は少しだけ時間をとって、
着物をそっと広げてみませんか?
クリーニングやお手入れにお困りの際は
お近くの紀久屋までお問い合わせくださいね!
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました♪
◆お電話でのお問い合わせ◆
(定休日:毎週火曜日)岡山本店:086-232-7766倉敷店:086-422-2100津山店:0868-32-5298四万十店:0880-31-2150◎おすすめブログ◎